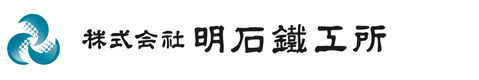近畿
1300年以上前の大昔から、今の首都にあたる「都」がおかれ、150年ほど前の明治時代に首都が東京にうつるまで、京都や奈良をはじめ、近畿地方は長く日本の中心地でした。今でも西日本の中心として、商業や工業が盛んです。
・北と真ん中と南で気候が大きく変わる … 日本海側の北部は冬に雪が多く、瀬戸内海の中央部は雨も雪も少なく安定した気候、太平洋側の南部は夏に雨が多いです。
・2つの盆地から歴史が始まった … 今から1000年以上前の昔は京都盆地と奈良盆地を中心に町が発展しました。天皇が住む都が置かれた奈良や京都は、今もたくさんの古いお寺や建物が残っています。
・日本一大きな湖、琵琶湖 … 滋賀県の約6分の1を占める琵琶湖は、日本一大きな湖です。その水は飲み水や農業、工業のために生かされています。
・林業が盛んな南部 … 南部には紀伊山地があり、雨が多くて木がよく育つので林業が盛んです。奈良県の吉野杉がとくに有名です。和歌山県は「木の国」と呼ばれています。
知っておきたいポイント
〈大阪や近江(滋賀)で商業が発展〉
近畿地方では、ものを売り買いしてお金をかせぐ商業が発展しました。とくに、古くから日本の商業の中心地として栄えた大阪、近江商人で知られる滋賀が有名です。人やものの行き来が多かったため、商業が発展しました。
〈大阪湾沿いを中心に阪神工業地帯が広がる〉
日本の三大工業地帯のひとつで、戦前は繊維工業が中心でした。今は海沿いに大きな石油化学の工場、内陸部には日用品などをつくる中小工場が集まっています。
〈日本海、太平洋、瀬戸内海での漁業〉
それぞれの海でとれるものや漁業の方法がかわります。日本海は若狭湾のサバ、瀬戸内海では明石のタコ、太平洋の和歌山県太地町はクジラのまちとして有名です。京都府北部の伊根集落は漁業と生活が一体になっています。
〈近畿地方を支える琵琶湖と淀川〉
琵琶湖の水、生活はもちろん農業や工業にも使われていますが、よごれた水が流れ込み、問題になった時代もありました。琵琶湖の水は使えなくなっては大変なので、今は大切にされています。大阪は都があった京都と淀川でつながっていて、さらに海ともつながっていたため、人やものの行き来が盛んになり、ものを売り買いする商人のまちとなりました。