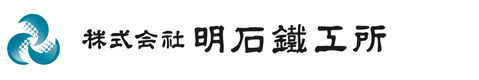中部
日本海側の「北陸地方」と内陸部の「中央高地」に大きく分かれ、さらに太平洋側の「東海地方」をふくむことがあります。3つのエリアで、気候や産業は異なります。
・「北陸地方」 … 夏は山からの風で気温が上がる、冬は雪がとても多いです。
・「中央高地」 … 夏は雨が少なめで夜は涼しさを感じる、冬は雪が少なめでとても寒いです。
・日本海側は米、内陸はフルーツ … 北陸地方には越後平野や富山平野など、米どころがたくさんあり、中央高地の盆地はモモやリンゴなど、フルーツづくりが盛んです。日本海での漁業、きれいな水や空気をいかした精密機械工業も発達しています。
・日本アルプス … 本州の中央に連なる飛騨山脈(北アルプス)、赤石山脈(南アルプス)を合わせて「日本アルプス」といいます。
知っておきたいポイント
〈広い平野と豊かな水で米どころが多い〉
生産量が日本一の新潟県をはじめ、日本海側は広い平野とゆたかな水で、米づくりが盛んです。冬は雪で農作業ができず、米だけを作る農業が多いです。(北陸は農地が80~90%が田んぼです。)
〈内陸部はフルーツ作り〉
長野県や山梨県の内陸部は、盆地の気温差を生かしたフルーツ作りが盛んです。長野県はリンゴがとくに知られ、山梨県はブドウやモモの生産量が日本一です。ブドウからつくられるワインも有名です。
〈冬に農作業ができないため伝統工業が発達〉
ゆきが多い地域では、家の中でも手作業でできる伝統工業が発達しました。石川県の輪島塗や九谷焼などが有名。冬の手工業は今も受け継がれ、福井県はメガネのフレーム作りが有名です。
〈寒い気候を利用した農業が発展〉
春になって溶けた雪は、豊富な水となり、山の中の田んぼを中心に米作りにも使われます。また、夏の涼しさを生かして中央高地で高原野菜栽培がなされ、気候をうまく利用しています。
〈雪や寒さのおかげで工業も発展〉
農業ができない冬にお金を稼ぐため、手作業の伝統工業が発達。豊富な雪解け水は水力発電にも使われます。富山県では多くの水と電気が必要なアルミ産業が発展しました。
〈中央高地は北海道や東北地方より南にあるが寒い〉
日本アルプスをはじめ、全体的に高い場所にあるため、長野県の軽井沢は北海道の札幌と同じくらいの平均気温です。