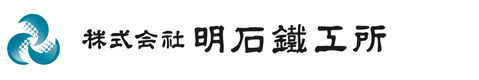『発災後のくらし方』
当たり前の暮らしが、ある日突然奪われてしまう。被災後の厳しい状況の中、少しでも安全安心に生きるための知恵と情報をまとめました。

1、被災後どこで暮らすか
『自宅か、避難所か、判断のポイントを知る』
≪どこで過ごすかは、2段階で判断する≫
建物の当面の使用可否について、自治体が応急危険度判定をします。自治体などからの指示が特にない場合、被災後に自宅にとどまるかどうか、2段階で判断するとよいでしょう。また、避難所だけでなく、一時的に、遠方の知りあいを頼ることも検討しましょう。
判断①危険を極める
↓不安に感じたり危険と判断したら避難所へ
危険がなければ判断②へ↓
チェックポイント
・自宅の家屋に被害があるか?倒壊のおそれがあるか?
・隣家の倒壊などで自宅に影響があるか?
火災、津波、液状化などの二次災害の心配はあるか?
判断②生活ができるか確認
不安がなければ自宅にとどまる在宅避難へ↓
↓自宅での生活ができなければ避難所へ
チェックポイント
・他人のサポートがなければ、暮らしていけないか?
【在宅避難】
【避難所】
※応急危険度判定が実施された場合は、判定結果にしたがってください。
≪自宅から避難するときに確認すること≫
自宅から避難所などへ避難するときは、以下のことに注意します。
・電気のブレーカーを落とす
倒れた家財の中にスイッチが入った状態の電化製品があると、通電再開後、漏電などによる火災のおそれがあります。
・ガスや水道の元栓を閉める
ガス漏れや漏水の可能性があるので、念のため閉めます。
・鍵はしっかりとかける
空き巣などに備えて防犯対策はしっかりと。玄関や窓の鍵だけでなくカーテンも閉め、できる範囲でレジャーシートを貼るなど割れた窓ガラスの補修もしましょう。
2、在宅避難の過ごし方
『安心して過ごせるひと部屋を確保する』
≪部屋を片付けるときの注意≫
スニーカーを履く、手袋をするなど、ケガをしない服装で。片付けには、停電していても使用できる、充電式掃除機やほうき、粘着クリーナーやガムテープが役立ちます。なお、片付けで出たゴミは分別し、各自治体が設置する仮置場ができるまでは自宅で保管を。
≪割れた窓の応急処置をする≫
割れてしまった窓は、窓枠から落ちそうな破片を取り除いたうえで、粘着力の強いテープを使いブルーシートやレジャーシート、段ボールなどを貼って、窓をふさぎます。
≪ボランティアによる支援を受ける≫
自宅の片付けなどにボランティアの手を借りることもできます。詳しくはお住いの自治体、または社会福祉協議会などにご相談ください。
『在宅避難での食事と料理』
≪被災時も活躍する調理グッズ≫
・カセットコンロとガスボンベ … 被災時、電気やガスが止まっていても温かい物が食べられる。
・鍋や深めのフライパン … ひとつで何役も。
・ピーラーとキッチンバサミ … 雑菌がつきやすいまな板を使わずに調理できる。
≪節水料理と節水家事を試してみる≫
水を節約するために、節水料理や食器類を洗わない工夫などを試しておきましょう。
・ウエットティッシュでスプーンを拭く
・食器にラップをかぶせる
・フライパンにアルミホイルを敷く
・使い捨て手袋をして調理する
『在宅避難での防犯』
≪空き巣対策のひとつとして在宅アピールする≫
空き巣犯に狙われないよう、在宅をアピールしましょう。
玄関先に電池タイプの人感センサー付き防犯灯を設置したり、一時的に外出する際はベランダに洗濯物を干しておくのも有効です。ただし、干したままにしておくとは、留守を悟られるので注意しましょう。
≪突然の訪問者には要注意≫
過去、震災を便乗した、詐欺や悪徳商法なども報告されています。ガスや電気の点検、家屋の修繕を装って高額な費用を請求されたなどの被害がありました。突然の訪問者が来ても、すぐに家には上げず、身分証明書の確認をするなどの注意が必要です。ひとりでの対応やその場での判断をしないことが大切です。
≪外出時は、戸締りと警戒をいつも以上に≫
自宅を空けるときは、割れた窓ガラスが外から見えないように目隠しする、ドア枠がゆがんで閉まらない玄関扉は、ドアチェーンと南京錠で施錠したり、部屋の電気をつけたままにするなど、できる限りの対策を。また、女性や子供は、ひとりで出歩かないようにして、防犯ブザーや笛を携帯しましょう。
3、避難所での暮らし方
『避難所での環境つくり』
≪プライバシーに配慮してマナーとルールを守る≫
集団生活では、互いのプライバシーへの配慮やマナーが大切です。近年の災害では、消灯後にゲーム機や携帯電話の画面が明るくて周囲の人が眠れないというトラブルも。ゴミ捨てや消灯時間、物資の配給など、避難所ごとの生活のルールをしっかり守りましょう。
≪着替えや洗濯干しは、専用のスペースで≫
集団生活のマナーとして、着替えや洗濯干しは、避難所内に設置された更衣室や物干し場を利用しましょう。
≪避難者も、役割分担をして助け合う≫
助け合いながら生活するために、避難者も可能な範囲で役割分担をして、できることや得意なことを、進んで手伝いしましょう。避難所をよりよい環境にするために、可能なら自ら運営に参加しましょう。
『避難所での配慮』
≪周囲からの積極的な声掛けを≫
子供は大人と違った形で不調が現れる傾向があります。また、高齢者や障害のある方は環境の変化で心身の不調を起こすこともあります。何か困っていることはないか、お手伝いすることはないかなど、声をかけましょう。外見からは配慮や援助を必要としていることがわからないこともあります。配慮を必要としていることを知らせるヘルプマークなどを身につけていないかにも気を配りましょう。
≪日頃から顔の見える関係を作る≫
高齢者や妊婦、難病の方や障害のある方などは、避難などが迅速にできないことがあります。日常の付き合いを通じて、避難場所や避難方法、非常持ち出し品など、発災時の対応を話し合っておけば、いざというときの安心につながります。
≪やさしい言葉で外国人の不安をやわらげる≫
地震が起きにくい地域から来た人は、未経験の地震に強い不安を覚えているかもしれません。簡単な言葉でも声をかけるなど、不安感を抱かせないような配慮が必要です。多言語に翻訳できるアプリを活用するのも有効です。
『避難所での体調管理』
≪トイレを気にして水分補給を我慢しない≫
水分不足は、脱水症だけでなく、さまざまなトラブルの原因になります。トイレの回数を減らすためにと我慢せず、こまめに水分を補給しましょう。
水分不足による不調 … 脱水症、低体温症、心筋梗塞、便秘、脳梗塞、膀胱炎、等。
≪からだを動かしてエコノミー症候群を予防≫
車中など窮屈な空間で長い時間同じ姿勢をとることで血流が悪くなり、血栓(血の塊)ができてしまうエコノミー症候群。血栓が血管に詰まると、最悪の場合、死に至ることもあるので予防策を覚えておきましょう。
≪むし歯や歯周病を予防するため口腔ケアも忘れずに≫
避難生活では、食生活の偏りや水分不足、ストレスなども重なり、むし歯や歯周病になりやすくなります。歯ブラシがないときは、少量の水やお茶でうがいをしましょう。ハンカチやティッシュペーパーを使って歯の汚れを取ることも効果的です。
≪心のストレス反応はひとりで抱えず相談する≫
不安や悲しみ、喪失感のほか、自分を責めたり、周囲の人への怒りなど、被災時の精神的な動揺の多くは、誰にでも起こりうる反応です。信頼できる人や、避難所に派遣される医師などの医療者、カウンセラーなどの専門家に相談するなどしてサポートを受けましょう。
被災時のストレス対策 … 深呼吸をする、信頼できる人に話を聞いてもらう、好きな香りを嗅ぐ、音楽を聴く、暖かい物を口にする、等。
≪できるだけ動いて生活機能の低下を防ぐ≫
避難所生活では、からだを動かす機会が減るため、筋力が低下したり、関節が硬くなるなどして、徐々に動けなくなることがあります。また、動かないでいると、だんだん心が沈んでくることも。これらの症状は「生活不活発病」と呼ばれています。身のまわりのことは、なるべく自分で行い、できることには参加することなどが予防になります。声をかけ合って、積極的にからだを動かしましょう。
≪被災時の不眠は自然な反応と知っておく≫
震災などの直後に眠れなくなるのは、危機的状況に対処するための自然な反応です。時間が経つにつれ、不眠は徐々に改善していきます。
避難所で眠るための対策 … アイマスクや耳栓をする、パーテーションを作り周囲の視線をさえぎる、段ボールなどで冷気対策をする、等。
不眠時に心がけること … 消灯時間に眠らなくてはと身構えず眠れるときに眠ると気持ちを切り替える、日中は太陽の光を浴びたり活動するなど昼夜のメリハリをつける、ウトウトしたら昼でも眠る、等。
『避難所での防犯』
≪貴重品は肌身離さず持ち歩く≫
自分のスペースを離れる際は、貴重品を持ち歩くようにするか、家族など信頼できる人に留守番をお願いしましょう。また、寝ているときには、肌身離さず眠るなどの対策も必要です。
≪他人の前では、お金などの話はしないよう注意≫
不特定多数の人が共同で暮らす避難所では、どこで、誰が話を聞いているかわかりません。トラブルを避けるため、お金や聞かれたくない個人情報の話は離れた場所でするなどの注意をしましょう。
≪複数人で行動して身を守る≫
犯罪の危険を少しでも減らすため、可能な限り、単独での行動は避けます。自宅に戻るなど避難所から離れる際も、家族や友人などと、複数人で行動するように心がけましょう。また、トイレや着替えをするときは、使用前に不審な点がないかを確認し、見張りを立てるなどの対策をしましょう。
≪死角になる場所にはできるだけ近づかない≫
日中でも人気のない場所や、周囲の目が届かない場所などでは犯罪にあう危険があります。外出時は、防犯ブザーを持ち歩きましょう。死角になる場所には、ひとりでは近寄らないように注意を。
≪子供だけの環境は作らない≫
男女問わず子供を狙った痴漢行為や、見知らぬ人からストレスのはけ口として怒鳴られたり叩かれたりといった信じられない事例もあります。子供だけの環境は作らず、常に大人が付き添っていられるようにすることが大切です。
≪見ないふりはせずに助け合う心を≫
もし、セクハラや暴力の現場に直面した場合、見ないふりや知らないふりをしないように。「自分が被害にあったら?」と考えて、助け合いの心が必要です。性的な犯罪や暴力を受けた場合は、ひとりで抱え込まず、警察や専門の相談機関、信頼できる人などに、まずは相談してみましょう。
『生活再建に向けて』
被災して住宅を失ってしまった場合に、利用できる様々な制度があります。まちの復興とともに、暮らしを立て直し、自立に向けて準備していきましょう。
≪罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を取得する≫
「罹災証明書」とは、地震や風水害などの災害で被災した家屋の被害程度を区市町村が調査し、公的に証明するもの。各種の被災者支援制度や給付金を受ける際、応急仮設住宅へ入居申請する際など、さまざまな場面で必要になるので、被災時にお住いの区市町村から取得しましょう。
≪経済支援制度を利用する≫
家族が死亡した場合の弔慰金や、生活再建のための支援金、融資のほか、税金の減免など、さまざまな経済支援制度があります。また、地震保険、自然災害共済に加入している場合は、保険金、保証を受けられます。
※ 詳しくは被災時にお住いの区市町村や管轄する税務署などにご確認ください。
≪応急仮設住宅などの住宅支援≫
住居を失った場合には仮住まい先として、建設型の仮設住宅や、自治体が民間の賃貸住宅を借り上げて提供するみなし仮設住宅などがあり、居住期間は原則2年間となります。そのほか、応急修理や建て替えなどのための融資制度もあります。
※ 詳しくは被災時にお住いの区市町村にご確認ください。